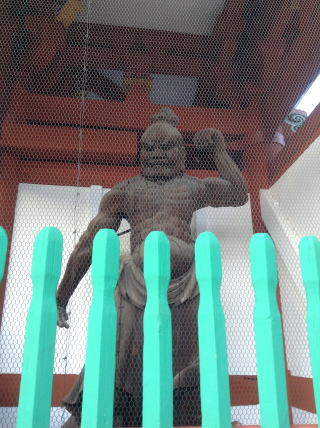第五番 紫雲山 葛井寺 参詣日 2023年11月2月
今回も熊野古道紀伊路の後というか、明日からの四国八十八箇所遍路の前日というか、狭間の時間
を使って西国三十三観音の1寺、葛井寺(ふじいでら)に立ち寄りました。
大阪阿倍野駅から近鉄南大阪線の準急に12分乗車すると藤井寺駅に着きます。駅から南東方向
に進むと藤井寺一番街の入口があり、その中を歩くこと約300m。5分ほどで到着です。近いです。
駅から近いのは素朴に嬉しいです。

藤井寺一番街
すでに11月となり、日の入りも早くなってきました。時刻は16時過ぎですが、もう夕闇が迫ってきて
います。