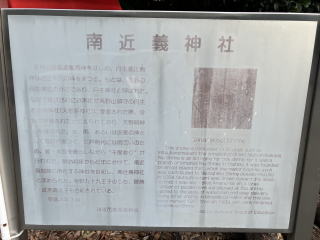2023.10.5(木) 晴
熊野古道・紀伊路 (大坂府:久米田~泉佐野)
参加メンバー 一人旅
5月に続いて熊野古道紀伊路を歩きました。
紀伊路の大阪府内のうち、久米田駅から先の泉佐野駅までの区間です。
四国八十八ヵ所遍路の前日の時間を使ってのショートトリップです。
1日休みを取り、一気に和歌山県との県境の山中溪までとも思いましたが、さすがに1日で歩くには
距離が長いですし、そうそう仕事も休めないので、午前中仕事をして午後から出かけることにしました。
このため現地に着いて歩き始めることができるのは14:30頃。この時期の日没が17:30頃なので、
約3時間の旅となります。泉佐野駅の周辺は町中で明るいので、陽が落ちても何とか歩けるでしょう。
本来の山酔会の活動とは違いますが、熊野古道はなかなか面白いですので紹介したいと思います。
歩行距離 累計距離 (八軒家船着場を起点として計算しています。)
38.2km
久米田駅
↓ 14.6km 52.8km
泉佐野駅
行程
久米田駅 → 麻生川王子 → 南近義神社 → 加支多神社 → 佐野王子 → 泉佐野駅
40 45 20 35 20
午前中は仕事をして、駅までダッシュ。JR大阪環状線に乗り換えて天王寺駅へ。四国遍路用の荷物
は重いですので、途中の天王寺駅でコインロッカーに荷物を預け、阪和線の快速で久米田駅に向かい
ます。乗り換えの駅ではホームや階段を駆け足で移動。少しでも早く着こうと頑張りました。
おかげでJR久米田駅に14:20に到着。何とか予定の時間に着けました。天満橋から南の和歌山に
向かって歩いているので、進んだ分だけ歩き初めの起点の駅までどんどん遠くなります。(近くなる
はずはありませんが、今後の課題です。今日のように午後から出かけて半日歩くという作戦は、
できないですね。)
台風14号は日本には近づかずに中国大陸の方に向かってくれたのですが、その余波というか、
派生した低気圧の影響で、週末の天気予報は今一つです。
今日の空も半分くらいをどんよりとした雲が覆っています。
駅の改札を出て駅前の通りを西に直進。府道30号線に出て右に曲がり南に進みます。
この付近に池田王子の跡地があるそうですが、民家の敷地内ということですし、説明板だけとのこと
なのでパスしました。
駅前の通りに「久米田駅前商店街」と書かれた提灯が並べられています。明後日の7日からお祭りが
あるようです。そういえばこの辺りはだんじりで有名な岸和田です。「岸和田市八木祭礼」という看板が
ありました。ここも山車が出るのでしょうね。

提灯の櫓
右折したところから500m程進むと左手に鳥居が立っていますが、これは積川神社の遥拝鳥居で、
この鳥居の額には「正一位積川大明神」と書かれています。これは寛治4年(1090)に白河上皇の
熊野御幸の際に書かれたものの模写で、実物は積川神社に社宝として保存されているそうです。
その積川神社はここから5kmも東にあるのでパスしました。(写真は撮り忘れました。)
続いて作才町の交差点の手前に「和泉式部歌碑」の看板がありましたが、肝心の碑は跡形もなく
なっていました。他の方のブログでは数年前まで道路横のフェンスで囲まれた空地の隅にぽつんと
碑があったようですが、今日は何もありませんでした。
その先の作才町の交差点を過ぎると府道から別れ左手に進みます。こちらが熊野古道ですので。
道が狭くなったおかげで車がいなくなり、安心して歩けます。
ところが、持っている紀伊路の案内地図では500mほど先で「道ノ池」というため池があり、その
手前で90度右に曲がり府道に戻るようになっています。
ですが池がありません。あるのは新興の住宅地と思しき一角です。不動産会社の「住宅売り出し中」
の看板があります。別に持ってきた道路地図を見ると池自体がなくなっています。
どの家も真新しいので、ひょっとしたら池を埋めた立てて宅地にしたのかもしれません。住宅地の
間を抜けて左に曲がると府道30号線の「土生」という交差点にでました。私の勘が当たっていたよう
です。
JRの東岸和田駅を通り過ぎていました。この交差点を左に曲がり、南に向かいます。
その先で津田川に架かる虎橋を渡って進みます。この川が市境で貝塚市に入ります。14:55。
5分ほど歩くと右側に「三和製作所」という会社があり、そこが「麻生川(浅字川)王子跡」とされている
と資料に書かれていましたが、建物の敷地内に入るわけにもいかず、王子跡の遺構は探せないかと
思っていたら、入口のすぐ右側に鳥居と御社があります。東屋もありました。その横の位置の塀の所に
わざわざコンクリートブロックが置かれていてその鳥居などがよく見えるようになっています。
ひょっとしてこれが「麻生川(浅字川)王子跡」で熊野古道を歩いている方用にコンクリートブロックが
置かれているのでしょうか?確認はできませんでしたが、その確率は高いと思います。
写真を撮らせていただきましたが、建物の内部ではないですから特に問題はないと思います。

麻生川(浅字川)王子跡?
また府道30号線を歩きます。この辺りは道がまっすぐです。次の信号で左手に入ると堂ノ池という
ため池があり、その先に「半田一里塚」があります。ですが信号の所で曲がるところが見つかりま
せんでした。50mほど進んだところの左側に堰堤のような物を見かけたので狭い通路を通って
そちらに向かうとビンゴ。池がありました。池の堰堤につけられた狭い道を進むと池の南の端の先に
「半田一里塚」を見つけました。15:10。
この半田一里塚はほぼ完全な形を残す数少ないものの一つだそうです。
説明板の左に「小栗街道の碑」、右側に「麻生川一里塚」の2本の石柱がありました。



小栗街道の碑 半田一里塚の説明板 麻生川一里塚
実は、熊野古道にも一里塚が設置されていましたが、江戸時代初期に東海道などの主要街道に
設置された一里塚ほど正確ではなかったそうです。平安時代の頃なので、そのころは時間も距離
もアバウトで問題なかったのでしょう。
右手に新井ノ池が見えてきたら、ここから住宅地の中を進みます。この辺りは道が入り組んでいて
かなりややこしいので、間違えたというか、そのまま30号線を直進してしまいました。
ほどなく線路を渡ります。左側に石才駅があります。これは水間鉄道という、厄除けの水間観音で
知られる水間寺と南海貝塚駅を結ぶローカル線です。
踏切を渡ったところにも池があります。ため池でしょうか?この辺りは池が多いです。
ちなみに、本来の熊野古道はこの池の東側なのですが、30号線を歩いているため、池の西側を
通っています。
この辺りは道が曲がりくねっていて本当にわかりにくいです。地図を頼りに進みます。
分岐となるところには「道しるべ地蔵」がありました。小さな祠からお堂のようなものまでいろいろあり
ます。よく見ると地蔵の祠の屋根に「右、おぐり(小栗)、左みずま」と刻まれていました。
その先に「清水大師堂」」という看板のある祠もありました。

清水大師堂
近木川に架かる福永橋を渡ると、「長谷川ノ坂」といわれる所に差し掛かります。江戸末期に有名な
疳(かん)医者だった長谷川氏の屋敷があることから「長谷川ノ坂」と呼ばれているそうです。
坂の両側には美しい石垣があり、昔の面影を色濃く残している町並みがありました。
もっと長いかと思っていましたが、ほんの100m位であっけなく通りすぎてしまいました。


長谷川ノ坂最上部 古い大きなお屋敷
坂を登り切り右に90度曲がると、その先で線路を渡ります。左手にJR和泉橋本の駅があります。
時刻は15:35。大体予定通りに歩いています。
その先の突き当たりを左折すると正福寺というお寺の先に地蔵堂があります。ここが「鞍持王子」
跡らしいとの伝承があるそうですが碑も何もありません。
この先に「南近義神社(みなみこぎじんじゃ)」があるはずなのですが、案内表示は何もありません。
先程の「長谷川ノ坂」もそうでしたがもう少し案内があっても良いのではと思います。
住宅街で神社やお寺を探す秘訣の一つが「大きな木を探せ。」です。前方にこんもりとした木立が
あります。おそらくあそこでしょう。
正解で15:45に南近義神社(みなみこぎじんじゃ)到着。
ここに「鞍持王子」と「近木王子」が合祀されているそうです。ですがここにも碑等は何もありません。
貝塚市はこうしたことに興味がないのでしょうか?確かにこの紀伊路の大阪府内の区間は世界遺産
に入っていません。そのせいかどうかわかりませんが、合祀などで片付けてしまった感が伝わって
きます。月日が経ちすぎ、開発という波にのまれてしまったのでしょうか?確かに周りを見渡すと完全
な住宅地で、昔の面影はありません。

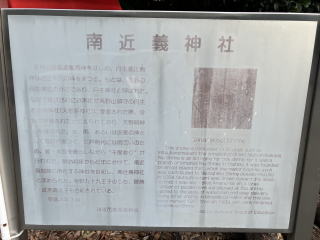
南近義神社(みなみこぎじんじゃ)
ですがそのようなこととは関係なく、この神社は水・雨・安産の神として信仰が厚いそうです。
境内に神社の説明板があり、それによると明治40~42年に近隣の神社をここに合祀して造られた
そうです。その時に「鞍持王子」と「近木王子」も合祀されたそうです。
近年に「合祀100年祭」があり、その時整備されたそうで、鳥居も新しく社殿の朱塗りが鮮やかでした。
楠木も涼しげに茂っていました。
少し南に吉祥園寺があり、その付近にかつて王子権現社(熊野神社)があり、それが近木王子の跡地
とされているそうですが、それを示すようなものは何もありませんでした。
その先で見出川を貝田橋で渡るとようやく泉佐野市に入ります。16:00。橋の先にある貝田町会館
という建物が貝田王子(鶴原王子とも)跡だそうですが、そこにも何もありませんでした。
(私が探せなかっただけかもしれませんので、「何もない。」は間違いかもしれませんが、実際の所、
資料や他の方のブログなどを見ても碑すらないのが事実のようです。)
近くにある加支多(かした)神社に明治40年に合祀されたらしいとのことなので立ち寄ってみましたが、
社殿横に貼られている由緒書き(神様の名前と境内社塔が書かれているもの)にも何も書かれていま
せんでした。16:05着。

加支多(かした)神社
この付近は池が多いです。四角池というネーミングそのままの正方形の大きな池の横を通ります。
鶴原南の交差点で国道26号線を右折して、次の信号を左折、すぐ先で斜め左に進みます。道ノ池
(東岸和田駅近くにも同じ名前の池がありました。紛らわしいです。)の横を進みます。
県道64号線に合流し、佐野川橋を渡った少し先に紅白に塗られた高圧線鉄塔があり、ここを左に
入ります。
案内書によると、「周りは田んぼで100m程先に進んで右に曲がると「佐野王子跡」がある。」となって
いますが、周りはすべて住宅。田んぼなどどこにもありません。ここも新しい家が多いので、田んぼを
埋め立てて宅地にしたのではと思い、大体の距離の目安をつけて右に曲がりました。
またもビンゴでした。住宅の間に小さな公園があり、そこに碑がありました。16:40着。



佐野王子の碑 熊野街道紹介板 佐野王子跡の石柱
佐野王子公園は小さいですが、熊野古道の案内板などもあり、昔の面影が残っていました。
ただ、碑は立派なもので公園もあるのでいかにもという場所なのですが、実はここが王子のあった
場所なのかどうかは定かではないそうです。ま、細かいことは気にせずに、これだけ立派な物を整備
していただいているだけでも良しとしましょう。
それから、私が利用している熊野古道の案内地図は少し古いようです。10年以上前のデータと
いう気がします。今回道路地図も持ってきましたが細かいところは案内地図を頼るしかありません。
「この地図は古い。」と認識して使うしかありません。
今日はここまでです。距離もすでに12km程歩きました。時刻は16:45になりました。
日も傾いて夕闇が迫ってきています。何より明日以降の四国遍路に負担がかかってはいけません。
泉佐野駅に向かいます。500mほど南に進み、泉佐野警察署の所で右に曲がり進むと南海電車の
線路が見えてきて泉佐野駅に到着です。17:00。
駅のホームから遠くに見えるのは関西空港の管制塔でしょうか?
ここから南海電車に乗り、新今宮に向かいます。新今宮駅でJR乗り換え、天王寺駅に到着。時間も
18時を回り、お腹がすきました。駅構内の立ち食いそばの店で夕食です。
「大坂でそば?」と思われるかもしてませんが、明日の朝食が四国の松山駅でうどんを食べる予定
なので今日は蕎麦です。大阪名物肉蕎麦に鳥天丼を食べました。味の方はご想像にお任せします。

肉蕎麦と鳥天丼
預けておいた荷物を受け取り、地下鉄とポートライナーを乗り継ぎ大阪南港に向かいます。
なぜ?と思われるかもしれませんが、実は、今回はフェリーで四国入りします。オレンジフェリーという
会社の航路ですが、大阪を22:00発、愛媛県の東予港に6:00着と便利な時間帯に運航されています。
お値段も飛行機やJR+ホテルよりも安く、船も大きく立派な物でした。シングルルームが取れました
ので1晩ぐっすり眠れます。


フェリーのエントランス 泊まったシングルルーム

大阪湾の夜景(ちょっと明るさが合いませんでした)
この後は四国八十八ヵ所第12回をご覧ください。
紀伊路の大阪府内も残すところあと1回の所まで来ました。
次回、11月に泉佐野から県境の山中溪まで歩く予定です。
大阪府内は町中の道路上を歩く区間ばかりでしたが、次回は多少山の中に入るようです。
熊野古道はまだ他にもルートがありますのでそちらも含めてチャレンジしてみたいと思います。
大昔から多くの人が歩いた道を歩くのは意義のあることだと思います。皆さんも歩いてみてください。