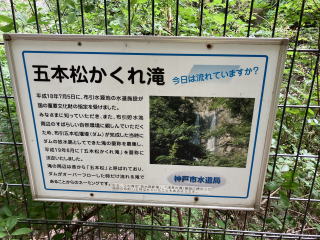2025.5.31(土)~6.1(日) 晴
六甲山全山縦走(の東側半分) (兵庫県)
931m
参加メンバー 私 Yさん Mさん Tさん Oさん (計5名)
昨年に続いて六甲山全山縦走に出かけて、前回歩き残した東側の半分を歩き(登り)ました。
六甲山全山とは、西は神戸市須磨区から東は歌劇で有名な宝塚へと連なる山域の総称のことです。
西側の区間は須磨アルプスとも称されていて、日本の近代登山発祥の地とされ、その黎明期には
小説「孤高の人」のモデルになった加藤文太郎氏達がトレーニングを積んだ場所です。
この話を聞いた時には、「そんな低い山でトレーニングになるのか?」と思いましたが、前回西半分を
登ってみて考えを改めました。充分登り甲斐がありました。
最高峰の六甲山の標高は931m。ですが東西にいくつもの山が連なっていて、その山々を全部つなぐ
と全長56km(43km~53kmの記述もあり)にもおよぶ全山縦走路が走っています。
これを1日で走破するのが、毎年11月に行われる「KOBE六甲全山縦走大会(神戸市主催)」です。
ですが1日での踏破は、夜明け前から日暮れ後まで十数時間を歩かないと(走らないと)走破できま
せん。トレランで走る方は6~8時間で走破するそうですが、さすがに歩きでは無理です。
現地までの移動の時間もありますので、全行程を2分割し、分けて歩く計画を立てました。昨年は西側
を、今回は東側の区間を1泊2日で歩きます。
宿は北側に有名な有馬温泉もありますが、さすがに土曜日の夜は無理。と思っていましたが、Tさん
のおかげでかなり高級な宿がお手頃価格で予約することができました。
まずは、新神戸駅からスタートし、市ヶ原経由で摩耶山に登るところから始まります。
さて、結果はいかがなりましたか、本文をお楽しみ下さい。
(行程)
1日目
JR新神戸駅 → 市ヶ原 → 掬星台 → 記念碑台 → ロープウェイ山頂駅
55 120 100 45
名古屋駅でYさんと合流して新幹線で新神戸駅に移動。ここでMさん、Tさん、Oさんが合流。
ここから前回打ち止めとした市ヶ原に向かいます。市ヶ原までは前回歩いたルートを逆に戻り、
市ヶ原から摩耶山に向かうルートである、稲妻坂と天狗道を経て、山上の掬星台(きくせいだい)を
目指します。
数日前まで雨の予報でしたので心配していましたが、雲は多いものの雨の心配はなさそうです。
9:05に駅を出発。まず、駅を出て新幹線の下をくぐって山側へ。その先の壁の前に20名ほどの
人だかりができています。壁に六甲山全山の地図があり、ガイドの方と思しき方が説明をしていま
した。ツアーのようです。この後ろについては大変だと早足で追い抜きました。
ちなみに、六甲山周辺は東西約20kmにわたる山域が瀬戸内海国立公園になっていて、これから
向かう「布引の滝」はもちろん、途中の道や「摩耶山」もその中に含まれています。

ツアーの方々
すぐ先に表示柱がありました。「布引の滝」までは約400m、陸上のトラック1周ほどの距離で意外と
近いです。(昔陸上をやっていたので、こうした距離間隔があります。)
民家の横といった場所に標識が建っていました。こうした表示がたくさんあり、助かりました。

標示柱
ちなみに「布引の滝」というのは4つの滝の総称で、「雄滝(おんたき)」「夫婦滝(めおとだき)」「鼓ヶ滝
(つつみがだき)」「雌滝(めんたき)」があります。
登山道ではなく普通の道を歩きます。最初に出会うのが砂子橋(いさごばし)です。知らない方は何気
なく渡ってしまいますが、アーチ式の石橋です。こちらは国の重要文化財に指定されています。明治時代
にこんな立派な橋を造ったのですね。それから100年以上使われているのがすごいです。


砂子橋
橋を渡って渓流の向こう側へ渡るとハイキング道が始まります。ここにも10名ほどの団体の方が
いました。会話からすると中国の方でした。
しばらく歩くと分岐点に到着。左に進むと「雌滝」です。せっかくなので立ち寄ります。左に進みます。
雌滝の所でこの団体の方から撮影を頼まれてしまいました。
昨日雨だったようで滝の水量が多かったです。

雌滝
ここから市ヶ原までは階段や整備された道が多く、遊歩道の周遊コースです。ただ階段がいくつか
ありますので、結構息が切れます。

周遊コース
次に出会うのが「鼓ヶ滝」です。テラスのような所がありますが、真ん中に石碑があり、ちょっと狭い
です。この滝は、滝壺に落ちる水音が鼓の音のように聞こえることからこの名前がつけられたという
ことですが、残念ながら私には聞こえませんでした。(写真はなし)
遊歩道はかなり混んでいます。外国の方も含めてたくさんの方が歩いていました。
続いて現れたのが「雄滝」です。高さ43mの落差の滝はかなりの迫力です。すぐ下には滝壺から流れ
ている「夫婦滝」もありますが、注目度は低めのようで、皆さん雄滝の滝壺の展望所に集まっています。


雄滝 夫婦滝
実際の所、「布引の滝」といえばこの雄滝の事なので、多くの人が写真を撮ったりしていました。
「雄滝」の横の階段を登ると、「お滝茶屋」というお店があります。飲み物や軽食などいろんなメニュー
がありました。ですが、さすがにこの時間ではまだ営業していませんでした。
その先の登り坂の途中には「みはらし展望台」があります。9:25着。眼下に神戸市やその先に海が
見えています。(ここは大阪湾というのか瀬戸内海というのか?)神戸空港があるポートアイランドや、
左手には大阪の町も見えています。こうしてみるとさすが日本第2の都市だと感じます。
前回来た時は雨でしたので景色もほとんど見えなかったのですが、今日は曇りですが、遠くまで見え
ています。
余談ですが、下の写真に見えているビルは115mあるそうで、ここよりも高いのだそうです。
ここにはトイレやベンチがあります。市ヶ原方面から戻ってきたときには、時間的にもここらで一服する
のにちょうどいいかもしれませんね。
私たちは歩き始めたばかりですので、景色を見た後休まずに先に進みます。


展望

説明看板
先に進みます。渓流沿いの遊歩道を歩いて進みます。

遊歩道
すぐ上には「布引ハーブ園」に向かうロープウェイがあります。かなり近づいた場所にあります。乗って
いる人が手を振ったりしています。心の中で、「自分の足で歩いてこそ価値がある。」とつぶやいて笑顔
で手を振り返しました。
本当に人が多いです。すれ違ったり、追い越しあるいは追い抜かれます。それなりの装備をしている方
は私達と同じく麻耶山に行く野でしょうね。
次に渡った橋は大正時代のはじめに造られた「谷川橋」です。普通に渡れますが、これも重要文化財
です。
「五本松かくれ滝」という看板がありました。名前の通り、松の木に隠れるように滝がありました。
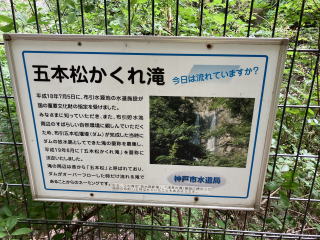

説明看板 五本松かくれ滝
その次が神戸の水がめといわれる「布引貯水池」です。1900年に日本で初めて造られた、重力式
粗石コンクリートダムです。9:40着。
正式名称は「布引五本松堰堤」。日本のダム湖百選に選ばれているそうです。(この手の百選が多い
です。)明治33年に造られたそうです。すごいですね。ご苦労されたことと思います。何せその33年前
にはちょんまげを結っていたのですから。
約60万立方メートルの水が溜められていて、これは神戸市で1日に使われる水の量とほぼ同じだ
そうです。たくさん使っているのですね。
余談ですが、「神戸の水は赤道を越えても腐らない」と言われ、昔の外国船の船乗りに大人気だった
そうです。そうした水が飲めることに感謝したいと思います。


重力式粗石コンクリートダム 堰堤


ダム湖 説明板
さらに上流へ進むと、「締切堰堤」があります。これも100年以上の歴史を持つ重要文化財で、「赤道
を越えても腐らない水」の維持の一端を担っています。
「分水堰堤付属橋」と、その奥にある「分水堰堤」は、川の水を布引貯水池に取り入れるためのもので、
布引の一番奥にある水道施設でもあります。
ようやく今回のルートの登山口である「市ヶ原」に到着です。10:00。新神戸駅からは2,3kmなの
ですが、布引渓流沿いは登り坂と観光する場所がたくさんあったので1時間かかってしまいました。
でも、ほとんどコースタイム通りの時間です。
ここにも「桜茶屋」茶屋があります。前回来た時は店先にドリンク類などを並べて販売していましたが、
今日はまだ開いていませんでした。近くには自動販売機もあります。
お店が開いていたら食事もできますので、お腹が空いている人は軽く食べてから入山するのもよい
かもしれません。
茶屋のすぐそばにはトイレもあります。ここから摩耶山頂まではトイレがありませんので、ここで済ませ
てから進んだ方が良いと思います。お借りしました。
ちなみにですが、茶店の前から河原に降りられます。河原は結構広くて、ここでバーベキューやランチ
を楽しむ人も多いようです。前回来た時には河原に50人以上の人がいましたが、さすがに今は誰も
いませんでした。
茶店の前を進んで摩耶山を目指します。いきなり山道に入ります。分岐に標識が建っているのですが、
直進。右折のどちらも天狗道経由で麻耶山に行けると表示されています。
調べたところでは、まっすぐ進むと「トエンティクロス」という緩やかなコースもありますが、右に進んで
最短距離の稲妻坂と天狗道を登ります。このルートは麻耶山に登る道の中で一番険しいと言われて
います。
これまで渓流沿いの散策路レベルの道を歩いてきましたので、当然といえば当然ですが、一気に険しい
道になり、そこを登っていきます。
道の周りが掘り返されています。猪の仕業でしょう、この辺りも出没しているのでしょうね。
ちなみにですが、これから登る摩耶山は、六甲山地のほぼ中央に位置しています。標高は702mで、
山頂付近からは、紀伊・河内・和泉・摂津・播磨・淡路・丹波・讃岐の八国が俯瞰できることから八州嶺
(はっしゅうれい)とも呼ばれていました。


山道に入る 分岐標柱
ところがこの標柱で間違えてしまいました。実は稲妻坂へはここをまっすぐ進んでもう一つ先で右に
曲がるのでした。
地図を読み間違えたのと、標柱に麻耶山と書いてあったのでそちらに進んでしまいました。
この時点では気付かずに、「さすがに稲妻坂は厳しいな。」などと話しながら登っていきます。
20分ほど登ったところで道の状況がかなり悪くなってきて、大きな石や木の枝などが道に転がって
います。土留めの木も半分くらい折れてしまっています。「あれ?」と首をかしげます。
地図と照らし合わせてどうやら旧道を歩いていることがわかりました。戻ろうかとも思いましたが、
このまま登れば稲妻坂に合流するようなのでこのまま進むことにしました。
さらに5分ほど登ったところで右手から道が合流します。10:25。これは「神戸布引ハーブ園」空の
道です。ロープウェイで神戸布引ハーブ園まで来て、そこからこの道にアクセスできるので楽をしたい
方は、このルートで途中までロープウェイを利用するのもひとつの手かもしれません。もちろん山酔会
たるものはそのようなものには乗りません。絶対に、きっと、多分、おそらく・・・。

合流点
さらに登ります。5分ほど登ると頭上に送電線があり、地図と照らし合わせて現在位置が再確認でき
ました。やはり旧道を登ったようです。すぐ下にはハーブ園の建物が見えています。
更に5分ほど登ったところで稲妻坂と合流しました。10:35。
この坂は、全山縦走参加者が、「ここを越えれば何とか最後までたどり着ける。」と認識する重要な
ポイントだそうです。確かにここを越えるとその先には大きな登りはありません。決意を新たに坂道に
取り掛かります。

稲妻坂との合流点
と思いきや、分岐からまずは下ります。「せっかく登ったのに。」とため息がでます。下りはわずかで
またすぐに登りとなります。実は今回歩いた道はほぼ全区間、登っては下り、下っては登る、この繰り
返しでした。
稲妻坂に入ってからはやはり人が多いです。トレイルランナーの人達の姿も結構見かけましたが、
軽快な足取りで走っていきますが、ここを走っている方はマナーがよく、すれ違ったり追い越したりする
ときは歩くというマナーを守っていましたのでよかったです。
さすがに稲妻坂は急坂ですが、登山だと思えば大したことはありませんでした。それから稲妻という
名前から相当ジグザグの道だと想像していましたが、それほどではありませんでした。
今日は曇り空で日差しはほとんどなく、おまけに風が強いので涼しくて助かります。といいつつも
上着は脱いでTシャツ姿になっています。
20分ほど登ると学校林道分岐に到着。11:00。ここからしばらくは平坦な尾根道となります。
ここが距離的には中間点といっても良いと思います。標高では2/3は登ったと思います。
道端に山アジサイが咲いていました。


学校林道合流点 山アジサイ
合流点の先はなだらかな登り道です。標高では山頂まであと200mくらいなので。ですがこの先には
天狗道の長い登りがあります。案内書には岩場の急斜面もあると書かれています。
でも200mを45分くらいで登るので、それほど大した登りはないと思うのですが。
その理由がわかりました。しばらく登ると下ります。天狗道には小さなピークがいくつもあり、登り下り
が繰り返されます。それも少しではなく50mくらい下るところもあります。何度も繰り返すたびに、
「せっかく登ったのに、下らなくてもいいのに・・・。」と考えるのは私だけではないでしょう。
トレイルランの方が多いです。さすがは六甲全山縦走路です。外国の方も多いです。さすがは神戸
ですね。
15分ほど登ったところで天狗道の醍醐味である岩を登るポイントが現れます。3点支持を意識して
慎重に登ります。登りばかりでなく下りもあります。岩場は上りよりも下りが要注意です。どこに足を置い
たら良いか考えながらゆっくりと移動するのがコツです。このコースは、なだらかな所や急なところと変化
が多いです。



岩場の登り 下り
実はこの天狗道は、いろいろな意味で全山縦走の時の最大の難所でもあります。「疲れ」、「足の痛み」
に続く第3の刺客である「人の多さ」に遭遇します。大勢の登山者(ハイキングの人も多く、中には小さな
子供を釣れた家族連れもいます。)で渋滞しています。何度も立ち止まり、なかなか前に進めない状況
になるそうです。
今日もすれ違いが結構ありました。私達でも「混んでいるなあ。」と思うのですから、時間に追われて
いる全山縦走者は「さもありなん。」と思います。
何しろ、人気コースの旬の時期なのですから仕方ないというしかありません。「休憩できて良し。」と
思ってすれ違いで待つしかありません。
幸い今日はそれほど混んでいなくて問題なく登れました。
5分ほどで岩場を登り切ったのでしょうか?道が平らになっていて、山頂まで1,5kmの標識が建って
いました。ここで休憩です。11:20。

標識
じわじわと暑くなってきました。曇り空で日差しはほとんどありませんが、やはり暑いです。
高度が上がるにつれ展望が少しずつ開けてきます。途中で見晴らしが良い場所がありました。眼下に
神戸市街地と海原が広がっています。その先には淡路島も見えています。海と町の両方を間近に望のは、
やっぱり不思議な感じがします。他の山ではまずこのような眺望は無いですから。
展望に励まされて再び歩き出します。体力的にはまだまだ大丈夫ですが、摩耶山の手前の急坂は
さすがに厳しいです。皆さんに「摩耶山頂は近い」と声をかけながら(半分は自分に言い聞かせながら)
登りました。
天狗坂の尾根登りの道を少しづつ登っていきます。前方に電波塔が見えています。あそこが山頂です。
もう少しです。と思ったらまた下りです。「なぜ?」という私の問いに誰か応えてくれないでしょうか?
その先は再び樹林帯の道です。周りの木はツツジです。ここは時期が合えばツツジのトンネルになって
いるそうです。残念ながらもう花は散っていました。
いつも思いますが、「ロープウェイで山頂まで上がってしまう人たちには、こういう楽しみは無い。」と。
まあ、苦労に応じたお楽しみがあるということです。そう思わないとやってられません。
あと少しで山頂というところにビュースポットがあります。大きな岩があり、この岩の奥には眺望が
広がっています。ですがスルーします。何故ならこの先の山頂の展望台からはもっと良い景色が見られ
ますので。
登山道が石段になります。実はこの石段が山頂に近づいた印、あと少しです。視界が開けました。
放送局の基地局と思しきアンテナがあります。その先に分岐があり、「山頂の三角点まで80m」の
標識がありました。11:45。
無事登り切りました。立派な登山でした。ちなみに六甲山は登山ルートが10ほどあるらしいのですが、
どれも大体同じくらいなのだそうです。
こうなると急に足取りが軽くなるから不思議です。小高いの丘?を上がると鳥居があり、「天狗岩大神」
と書かれた扁額がありました。すぐ横には巨石もあって、天狗の伝説の謂れが書かれていました。
「天狗岩大神」の横に、お目当の標識がありました。ようやく「摩耶山頂」に到着です。標高の基準となる
三角点もここにありました。11:50着。
ただ残念なのは、摩耶山の山頂からは、景色は全くありませんでした。

摩耶山山頂
ちなみに、摩耶山の謂れは弘法大師空海が摩耶夫人を安置したことが山名の由来だそうです。
山上の一角に再建された天上寺の摩耶夫人像は、女性のあらゆる難病や苦しみを救ってくださる
女尊であり特に安産と子授け・子育ての守護仏で女人守護の寺として信仰を集めています。
余談ですが、2週間前に四国に出かけ、八十八箇所歩き遍路を結願しました。弘法大師とのご縁
を感じます。
先に進みます。先程の舗装路まで戻り先に進みます。バスが停まっていました。このバスはここと
六甲ケーブル山上駅、有馬ロープウェイ山上駅を結んでいます。
バス停の所で右に進むと掬星台に到着です。12:00着。
ここは山頂というよりも山上公園といった方が良いです。本当に広いです。
掬星台の一角には、摩耶ケーブルカーの山上駅があります。また、ここまでバスで来れるそうです。
もちろんマイカーでもOKです。何と貸自転車までやっていました。
当然、ケーブルカーやバスを利用して登ってきた方がたくさんいます。仕方ありません。ここは「観光地」
です。市街地から手軽に登れる夜景の名所ですから。ですが歩いて登れば立派に登山が楽しめます。
また、それらの交通機関はエスケープルートにもなります。いざという時には助かります。
時間も頃合いなのでここで昼食です。山上広場のベンチに座ってもってきたおにぎりをほおばります。
いつもながらおいしいです。


掬星台(正面の建物は電波塔とロープウェイ山上駅) ベンチで昼食
展望台の「掬星台」は、「手で星が掬(すく)えるくらい高い所」という意味があるのだそうです。
ここは日本三大夜景のひとつに数えられていて、関西の方の夜のデートコースの定番だそう
です。その夜景は100万ドルの夜景と言われています。(是非一度見てみたいものです。)
一説によると、ここから見える範囲の1ヶ月間の電気代は1000万ドルだそうです。昼の12時なの
で夜景ではありませんが、見事な眺望が広がっています。南西には神戸市の中心街、その先に
ポートアイランドと神戸空港、そして大阪湾が広がっています。南東には大阪の中心街とおぼしき
街並みと大阪のビル群(一番高いのはあべのハルカス?)や関西空港も見えています。
万博会場と思われるところもかろうじて見えています。
阪神地方に来たのだなと実感します。先程までの急登の苦労と疲労も、この景色を目にすれば
吹き飛びます。(実際の所、飛ばずに残ってはいましたが。)


掬星台からの眺め 大坂方面 三宮方面

神戸方面
食亊と休憩の後、ここから裏山である摩耶別山を目指して出発です。 12:20。
全山縦走路の看板を見つけました。六甲山の山上は観光地として開発されていて、摩耶別山を越える
とここまでと一変して舗装路と整備された散策路の並走が始まります。散策路は土道です。
途中に観音像が安置されていました。



全山縦走路の看板と縦走路 観音像
お洒落で立派な「オテル・ド・摩耶」の横を通過して少し進むと左手に「摩耶山天上寺」があります。
大きな甍が見事なお堂です。12:35。

摩耶山天上寺
六甲ガーデンテラスへと向かいます。全山縦走路はここから奥麻耶ドライブウェイに並行するような
形で進みます。
その先に「アゴニー坂」という標識がありました。この名前は「あごに膝(ニー)がつくくらいに急坂だから」
と名付けられたのだそうです。ですが登ってみると大したことはありません。首をかしげているとその先で
激下りが始まりました。アゴニー坂はこちら側だったようです。10分ほどで降り切りましたが、この区間は
登るとなると一級品の登山の坂でした。確かにここを登る時は、膝を大きく上げないといけないでしょう。
実にナイスなネーミングでした。



アゴニー坂
坂を下りた後は車道に合流。横の歩道を歩きます。道は下っています。先程のアゴニー坂といい、
こんなに下ってはこの後また昇り返さないといけないのでやめてほしいのですが。

車道と歩道
この辺りには上高地の大正池に似ているとして命名された穂高湖や、明治初期に氷を切り出していた
三国池の横を通っていきます。少し離れたところからアナウンスが聞こえてきます。多分六甲山牧場で
しょう、ここは観光地でもあります。
道路の横には別荘がいくつも建ち並んでいます。夏は涼しくて良いでしょうね。
神戸市自然の家を過ぎた先で右手の縦走路に入ります。12:50。ここの登りも厳しいです。先程の
坂で下った分を登り返します。石段あり、土道ありの道は息が切れます。

縦走路に入る
途中で一旦下って登り返す地道を歩き、階段を登りきってドライブウェイに再び合流します。ここに東屋
がありましたので一休みします。13:25。
持っている地図ではほとんどわからなかったのですが、アップダウンがかなりあります。2点間の標高差
はわずかでも、累計標高差はその2~3倍はあると思います。
ここからは車道横の歩道をしばらく歩きますが、写真のように歩道に木が生えていました。もともと
あった木を残したのか、それとも後から生えてきたのか?どちらでしょうね。
ここからは、ひたすら車道を進むことになります。途中で1ヶ所、南に展望が広がっています。思わず
足が止まります。


合流点の東屋 木の生えた舗装路
今日は風が強いのでロープウェイが運行しているかどうか心配でしたが、この時ネットで調べて無事
運行していると確認できてほっと一息です。最も仮に休止していたとしてもバスとケーブルカーで神戸
側に下山することができます。
舗装路は登山道より歩きやすいですが、やはり地面が固いので膝に負担がかかります。何より通過
する車が最大の難物です。
T字辻に13:40に到着。
その先に六甲山の開祖、A.H.グルーム氏の胸像があるはずなのですが見当たりませんでした。
今日の六甲の繁栄の基礎を築かれた方です。
余談ですが、六甲山YMCAがありました。私の世代だと西城秀樹氏(故人)の歌で有名になりました。
ついつい歌を口ずさんでYMCAのポーズを取ってしまいました。元々はキリスト教系の団体の施設です。
その先には別荘やホテルが建ち並んでいます。どの建物もおしゃれですね。

六甲山YMCA
丁字ヶ辻の交差点を過ぎ、しばらく歩くと藤原商店があります。ここでは飲み物やカップ麺を購入
しての飲食ができます。そのほか夏にはスイカも食べられるそうです。縦走路中のオアシスの
ような存在です。こうして補給や休憩ができる所があるのは便利であり、有難いです。
ビールの幟旗に思わず引き寄せられそうになりました。
その先に赤い鳥居のある「白神稲荷神社」がありました。13:45。すぐ隣りの道路を車が走り、個人
の住宅もある景色は、ここが山上だと思えなくさせてしまいます。
ですが時々見える山麓の町や海の景色は、山の上にいるのだと気づかせてくれます。かなり西まで
来たのですね、大阪の町が真南にあります。淀川の河口が真下に見えます。


藤原商店 白神稲荷神社
舗装された縦走路をどんどん東へと向かいます。
一丸と立派な建物がありました。喫茶店の看板が出ていますが、ここは六甲山ホテルです。ホテル
の営業はしていないみたいです。
記念碑台に14:00到着。あと1時間くらいでロープウェイの山上駅に着けると思います。
すぐに登六庵のカレーライスの看板が目に飛び込んできました。時間さえ合えばここでカレーで昼食
でもと考えたのですが、ちょっと時間が合わないので断念しました。
ここに観光案内所のような施設があり、ベンチに腰掛けて休ませていただきました。トイレもありお借り
しました。
一休みして先に進みます。14:10発。記念碑台の先で縦走路は車道を離れ、縦走路に入ります。
少し看板がわかりにくかったです。もっとも、間違えたとしても、映画の八甲田山の「天は我々を見放した」
というセリフのような遭難の心配はありませんが、時間のロスはありますので。

全山縦走の分岐
この辺りには普通の民家が何件もあります。ここで生活するには大変だなと思いきや、実はここから
六甲ケーブルの駅までは1km足らず。神戸まで充分通勤ができますね。
さらに10分ほど民家の間を進むと、日本最古のゴルフ場の神戸ゴルフ倶楽部に到着です。
ゴルフ場の敷地の中の、ゴルフボール除けの金網の中を歩きます。ゴルフに熱中していたころは、
ぜひ一度ここでプレイしたいと思っていましたが、なかなか予約が取れませんでした。


神戸ゴルフ倶楽部
この辺りもトレランで走っている方が多いです。歩いている方ともすれ違います。さすがに人気があり
ますね。
さらに10分進んでみよし観音に到着。手を合わせて先に進みます。
ここから左に分岐する道があり、そちらに向かうと六甲高山植物園があります。標高865mの六甲山頂
付近に位置する植物園です。その標高を利用して、世界の高山植物や寒冷地植物を栽培しています。
その他にも六甲山の自生植物などを合計して約1500種を栽培しているそうです。
その先の道端に赤いツツジとピンクのサツキが咲いていました。


赤いツツジ ピンクのサツキ
ほどなく六甲ガーデンテラスへと到着しました。14:35。六甲ガーデンテラスは六甲山上の一大観光
スポットであり、大勢の観光客が訪れています。駐車場には多くの車が停まっています。この辺りだけを
見ると下界の町中と変わりません。
六甲枝垂れ(ろっこうしだれ)や六甲山ジンギスカンパレスなど、神戸を代表する名所・名店が
立ち並んでいます。のんびりと観光に訪れて楽しみたい場所です。
公共交通機関でのエスケープができるのはこの六甲ガーデンテラスが最後になります。ここから
先は縦走路終点の宝塚まで歩くしかありません。それが難しそうな場合は、バスやロープウェイで
下山するのが賢明です。私達も今日はここまでです。さすがにこの時間では宝塚までの縦走は無理です。
ロープウェイの駅に行く道を探しましたが見つかりません。全山縦走路の案内はあるのですが。
駅は縦走路から外れたところにあるようです。地図で見当を付けて進むと無事到着しました。14:45。
ロープウェイに乗り、一旦下山します。「今朝、ロープウェイなどには乗らないと言ったんじゃないか?」
という突込みはしないでください。そんな昔の事は忘れました。


有馬ロープウェイ
ロープウェイは15分ほどでしたが、なかなか良い景色でした。かなりの急傾斜を一気に降りるので
スリルがありました。おまけというか、今日は風が強く、結構揺れました。
このロープウェイで降りたところが有馬温泉です。山麓駅から温泉街を抜けて行きます。ここも人が
多いです。途中の日帰り温泉の前の足湯はイモ洗い状態でした。当然温泉の方も混んでいました。
当初はここで入浴して神戸市内まで電車で向かう計画でしたが、とても入浴はできなかったですね。
30分ほどで今夜の宿、エクシブ有馬御苑に到着。15:35。ここは館内の温泉が、有馬名物の金泉・
銀泉の2つともがあるという、豪勢な宿です。Tさんのご尽力で取ることができました。感謝です。

エクシブ有馬御苑
早速入浴です。さすがに日本三大名湯の1つに数えられている有馬温泉です。よかったです。
汗と疲れを流しサッパリしました。
ちなみに、金の湯は鉄分が多く赤茶色で、銀の湯は無色透明の湯です。
今夜の夕食宴会は、少し電車で移動しないといけません。実は有馬温泉の温泉街には、軽食の店
はいくつかあるのですが居酒屋のようなお店はほぼ0です。
宿から少し歩いて有馬温泉駅に到着。ここから電車で移動です。6駅ほど先にある谷上駅の近くに
あるお店まで移動です。「谷上笑店」という偶然見つけたお店でしたが、雰囲気も料理も良く、楽しく
飲んで食べ、語らいました。鹿児島にしかないと思っていた鳥刺しが食べられたのには感動しました。


谷上笑店 赤もつ鍋
2時間ほど楽しく過ごし、再び電車に乗って有馬温泉に帰ります。ほろ酔い気分でしたので、
電車の揺れが子守唄になってついついウトウトとしてしまいました。
幸い乗り越さずに無事に有馬温泉に到着。宿に戻ってもう1回入浴して、着替えて就寝。朝まで爆睡
しました。
このような立派な宿では緊張して眠れないなどと冗談を言っていましたが、そのようなことはありま
せんでした。(笑)
2日目
ロープウェイ山頂駅 → 最高峰 → 船坂峠 → 大谷乗越 → 塩尾寺 → 宝塚
55 70 60 70 45
朝5時過ぎに目が覚めました。さすがに21時に寝るとこうなりますね。
6時過ぎまでゴロゴロしていて、6:30から昨夜買っておいた朝食を食べます。
実はこのホテルのモーニングサービスは3,000円です。さすがに遠慮させてもらいました。
朝食を済ませて準備をして8:30に宿を出発。ロープウェイ山麓駅に向かいます。温泉街から
駅までは結構急な登り坂で、いきなり登山でした。

9:00にロープウェイ山麓駅に到着。始発に乗りたかったので、早めの行動です。これが大正解で、
10分前にはすでに行列ができていました。
9:30の始発に乗って山頂駅に向かいます。
今日は昨日より雲が少なく遠くまで景色が見えます。有馬温泉の北側に大きな住宅地がいくつ
も広がっています。意外でした。有馬温泉は山の中というイメージだったのですが。
よく考えてみれば有馬温泉からでも三宮まで30分くらいです。充分通勤圏ですね。


山麓駅とロープウェイからの眺め
9:45に山上駅に到着。準備をして歩き出します。
もっと早く歩きだしたかったのですが、何せ始発が9:30ではどうしようもありません。
反対側の六甲ケーブルに乗れば1時間ほど早く歩き出せたのですが、有馬温泉からだと2時間
以上電車やバス等を乗り継がないといけませんので、このルートにしました。
山頂駅を出発し、六甲山最高峰へと向かいます。9:50。この付近の標高はすでに800mを
越えていて、肌寒いくらいで山麓とはずいぶん気候が違うと感じます。ちなみに、山頂の気温は
13度でした。
夏は涼しくてよいのでしょうが、冬は積雪の可能性もあります。冬季は雪装備を用意して来た方
がよいでしょう。それよりも冬は止めた方が良いと思いますが、意外とお正月などに登る方も多い
そうです。
山上駅を出て一旦六甲ガーデンテラスへと戻ります。全山縦走路はこちらにありますので。
近道があり、ほんの3分で到着。昨日は車道を歩いたので遠回りをしていました。
案内標識に従って進むと、施設の西側の細い道を通って縦走路に出ます。9:55。
そこから石階段や土道が始まります。10分ほど歩いた所で南側が開けていて、眼下に大阪
の町が見えています。昨日の掬星台に比べるとずいぶん西に来たのがわかります。大阪湾が
真南に見えています。淀川の河口が見えていますので、その先にあるのが万博会場の夢洲
でしょうか?ミャクミャクが手を振っているのが見えます。というのは冗談ですが、今日もたくさん
の人が詰めかけているのでしょうね。


縦走路の石段 大坂湾
ウグイスが鳴いています。なかなか良い声です。
15分で極楽茶屋跡に到着。10:05。建物は何も残っていませんでした。跡地にベンチがあり、
腰掛けると景色を眺めながら休憩できますが、休まずに先に進みます。
途中で六甲山山頂にある電波塔が見えました。それほど距離はありませんが手前に谷が見えます。
アップダウンがありそうです。

六甲山山頂にある電波塔
極楽茶屋跡から先は、縦走路はほとんど県道16号線と並行しています。ガードレールのすぐ
外側に道があるところもありますが、県道と何度も交差しますので、そのたびに当然道路を横断
します。その先で再び山道に入ります。車道横断と山道、その繰り返しです。
この辺りの縦走路は距離的にはショートカットしているのでしょうが、結構アップダウンがあり
疲れます。



道路沿いの狭い縦走路 県道を横断 その先で登り
3回ほどこのパターンを繰り返した先で、道端に綺麗な藤の花が咲いていました。下界だとGW
くらいが開花の時期なのですが、ここは気温が低いせいか満開でした。
その先でまた縦走路に入ります。


藤の花 縦走路入口
そしてまた車道を横切り、縦走路に入るという繰り返しです。
今日もすれ違う方が多いですが、この方たちは縦走路を宝塚から逆走されているのでしょうか?
それとも山頂までの往復の途中なのでしょうか?


横断箇所 その先で縦走路
登山道は県道と付かず離れずの距離なのですが、登山道は意外とアップダウンを繰り返していて、
結構大変です。舗装路はなだらかですが、遠回りです。どちらが良いのか?
ちなみに、六甲全山縦走大会のランナーは、車道を走るそうです。
この日もトレランの方が山道に入らず、車道をそのまま走っていきました。やはり走るには車道
方がよいのでしょうね。
私達は登山道を歩きましたが、その利点は車がいないことです。車道は当たり前ですが、すぐ
横を車が走り抜けていきます。
ロープウェイ山頂駅から山頂まで高度差はわずか100mほどの登りなのですが、途中で谷が
3つほどあり、登ったり下ったりを繰り返しますので、累計ではかなりの登りがあります。ただ、
道は整備されていて、長い急登の箇所も無いので、歩行のペースは確保できています。
この辺りの登山道は本当にしっかりと整備されています。
縦走路を西に進み、少しづつ高度をあげていきます。前方の小高い丘の上に六甲山山頂にある
電波塔が近くに見えてきました。
9回目(多分)の交差箇所で車道を横断し、最後の登りはかなり長い階段状の急坂です。

最後の石段
そこを登りきると幅の広い車道に出ます。ですがこちらはドライブウェイではありません。
おそらく山頂にある電波塔に向かう道でしょう。
その道を進んで、最後に階段状の箇所を登りきると、六甲山最高地点に到着です。10:45。
ここの標高は931m。三角点に説明板があり、ここは現在も地質が隆起しており、阪神淡路
大震災後に標高が12cmも高くなったそうです。
とにもかくにも、本日の最高到達点がここです。山頂は平で結構広い広場です。大きな標柱と
三角点、小さなケルンとベンチがありますが、どう見ても山頂という感じがしません。すぐ近くの
駐車場に車を停めて登ってきたと思われる家族連れやグループの姿もみられます。自転車の方
もいます。その辺にある広場という感じです。
すぐ横に大きな電波塔が立っています。これには「残念」と思いますが、生活には必要ですから。

六甲山山頂にて
でも山の上にいるということが実感できものがあります。それは眺めです。南方向は見えません
が北方向が開けていて、この景色を眺めている分には山上にいると感じられます。
振り返ると六甲ガーデンテラスの建物が霞んで見えています。気づかない間に随分歩いてきて
いました。


六甲ガーデンテラス 北西方向の景色


北方向 北東方向
以前に来た時(もう30年位前にバイクツーリングできました)は、周りを樹木にさえぎられていて、
展望はありませんでしたが、今は樹木が伐採されたのか展望が広がっています。
一休みして最後の眺めを楽しみます。この先は展望がほとんどなくなりますので。
と思っていたのですが、風が強いです。帽子が吹き飛ばされそうな強さです。このため、5分ほど
で出発です。先程の舗装路を戻り、そのまま下ります。下りきったところに建物があります。トイレ
と休憩所です。
ここは「六甲一の立派なトイレ」だそうです。屋根のあるベンチもあります。ここで昼食にしました
が、さすがにトイレの前では食べる気がしなくて、近くの東屋の横で食べました。
この先には休憩施設はないようですのですので、座って食事ができるのはここが最後です。
いつものコンビニのおにぎりですが、いつも通り美味しいです。

トイレと休憩施設
余談ですが、トイレも使わせていただきましたが、なぜか小便器の水があふれて、水浸しでした。
まあ、施設としては立派だと思います。洗面所があり、手が洗えたのがありがたかったです。
すぐ横のドライブウェイ(県道16号線)の反対側に一軒茶店があり、こちらで食事もできます。
それにしても人が多いです。山頂での30人くらい、ここでは50人以上の人を見かけました。
ツアーの団体の方もいます。自転車のグループも、バイクツーリングの方もいました。
食事を終えて先に進みます。11:10。
この休憩施設から北側に向かう道があります。これは魚屋道(ととやみち)で、有馬温泉方面
に下山する事ができます。距離は約4kmで、約1時間半で降りられます。魚屋道はハイキング
コースとしても知られていて、普通に有馬温泉からの登り降りのルートとしても使われています。
ここを越えた先はもう宝塚まで降りるしかなくなります。
ここから東六甲縦走路に入りますが、ここからがまた一苦労です。終点の宝塚に向かって大下り
に入ります。何せ標高差はほぼ900m。その標高差を東六甲縦走路の約14kmで下ります。
その途中にはお店やトイレもありません。最後の踏ん張りどころです。「阪急宝塚駅まで14,8km」
の看板があります。とうとう宝塚の文字が出てきました。
ここから300mほど車道脇を歩きます。歩道がないのですぐ隣をかなりのスピードで車が走って
いくのはさすがに怖いです。


車道を歩く 縦走路入口
その先で道標の所から山道に入ります。ここからも車道と山道を交互に歩きます。アップダウン
があるのも同じです。途中には熊笹の中の道や掘割のような所もあります。少し進んだところで
神戸市を通り過ぎて芦屋市に入ります。

宝塚の文字
少し進むと前方にトンネルがあります。これは鉢巻山トンネルです。トンネル手前で左手に入る
山道があります。こちらの道を進むとトンネルの上部を越えていけるようです。が、笹で道が覆わ
れています。「芦屋市が道路の整備を手抜きしている。orほとんどの人がトンネルの方を通り
歩く人が少ないので荒れている。」のどちらなのかわかりませんが、ほとんどの方がトンネルを通る
そうです。私達もトンネルを通ることにしました。実際には歩けるようで入って行った方もいました。

鉢巻山トンネル
鉢巻山トンネルを通過。11:20。トンネルには端に歩道がありますが、一人がやっと通れる
くらいの幅です。トンネルの途中に市境の看板があり、「ここまでは芦屋市、この先は西宮市」
となっています。
トンネルを抜けた先で道路の脇に「石宝殿」という石の鳥居があります。参拝はせずに鳥居の
手前で手を合わせて先に進みます。

石宝殿の石の鳥居
ここからまた車道を歩きます。横を結構な台数の車が通り過ぎていきます。
300mほど進んだところに東六甲縦走路へと入ります。ここが六甲全山縦走路の全行程の
3/4の地点になります。11:25。
六甲山大縦走大会で、須磨から1日で歩き通す場合は、この付近で日暮れを迎えている事が
多いそうです。ヘッドライト光の帯が宝塚方面から見られるそうです。幸いまだ12時前です。十分
明るいのですが、足は疲労で悲鳴を上げています。


東六甲縦走路への入口
ここから宝塚市まで「12km/約3時間」と書かれています。「頑張れー!」の文字も見えます。この
先の区間はトイレも売店もなし。エスケープルートもありません。最後の難関です。
「宝塚まで12,1km」となっています。「あれもう2kmも歩いたのか?」と思いますが、縦走路を
歩いたのでショートカットしたか、あるいは距離があいまいなのかのどちらかでしょう、15分で2km
は歩けません。
道標があり、番号が付けられています。ここは1で最後は36だそうです。この数字が励みになります。
東六甲縦走路は、最初はやや荒れた道が続きます。「ザ・登山道」という道です。しばらくは
悪戦苦闘が続きます。



急降下の道
道幅は狭いところはあるものの、全体的には十分な広さが確保されています。ですが、小さい
とはいえアップダウンもかなりあります。決して下り一辺倒ではありません。何しろ、水無山(804m)
太平山(681m)、岩原山(573m)、譲葉山(514m)、岩倉山(488m)と5つの山を越えていか
なければなりません。(山頂を通る訳ではありません。)
当たり前ですが下りが続きます。登山は登りよりも下りの方が事故が多いのです。特に下山で
山麓まであと少しという所での転倒が要注意です。疲れで足が上がらなくなり、躓くのが原因です。
縦走大会でもこの区間の事故が一番多いそうです。
ところがずっと下りばかりではありません。地形の関係なのでしょうが、しばらく降りると必ず登り
返しがあります。距離は短いものの登り返すのは精神的にも堪えます。
登山道の横にある標識はいずれも「六甲山縦走路」の標識だけです。水無山はもう過ぎたのか
まだなのか不明です。
この辺りでもウグイスが数羽鳴いています。なかなか良い声ですね。
笹藪の中の緩やかな道を進むと「21」番の番号の入った標柱がありました。大平山の文字が
あります。どうやら水無山は通り過ぎてしまったようです。


笹藪の中の緩やかな道 21番の標柱
数か所かなりの急坂もありました。体力を消耗し、疲れもピークですので、慎重に降ります。
道自体は土道で歩きやすいのですが、所々にある階段は歩幅が合わず、歩きにくいです。
12:20に「船坂峠」に到着。なかなか快調なペースで歩いています。標柱の番号は29です。
2km歩いたのに番号は2つしか変わりませんでした。
周りを熊笹に囲まれたところです。峠感は0ですね。左手に分岐しているのは清水道です。
ここを下ると有馬街道に出て、船坂というバス停から宝塚に行けるそうです。
この辺りは小さなアップダウンを繰り返しますが、標高差はあまりないので快調に進みます。
この辺りの標高は740mなので山頂から200mほど下りました。

船坂峠
さらに進むと杉林の中の道にと変わりました。木漏れ日が差していて良い雰囲気の所です。

杉林の中の道
一休みして先に進みます。途中で東方向が開けているところがありました。12:50。西宮の
町並みが眼下に広がっています。手前の西宮のシンボル「甲山」が目印です。その他にも北山
貯水池、阪神競馬場に大阪の高層ビル群が良く見えます。川は武庫川でしょう。
かなり西まで来ましたが、あそこまで降りないといけません。まだまだ先は長いです。

西宮の町並み
12:55にまた舗装道路に出ました。すぐ先に鉄塔が建っている小山があります。おそらくは
あそこが大平山でしょう。山頂まで行く道があるようですがスルーしました。
ここからしばらくは舗装路を歩きます。「ここを誰が通るの?」と思いましたが、ちゃんとガード
レールもあります。おそらく先ほど見た鉄塔(おそらく電波塔)に行くためのものでしょう。
車道を少し歩くと、また右側に縦走路の入口があります。13:05。

縦走路入口
ここからもどんどん下ります。でもまた登り返しがあります。結構小刻みに登り返しがあり、疲れた
足と体には厳しいです。特にここは長い距離の登り返しでしたので堪えました。
縦走路は林の中で道の周りは木が生い茂り景色は全くありません。途中の道標の数字が増えて
いくのが唯一の励みです。
20分くらい下ったでしょうか?また舗装路を横断します。ここが大谷乗越です。13:20着。ここで
休憩です。32番の標識がありました。それから、ここから標柱の表示が近畿自動車道に変わって
いました。
この道路を走る車はどのくらいいるのでしょうか?立派な舗装路がもったいないような気が
します。それから、ここの標高は540mなので山頂から400mほど下りました。


大谷乗越
大谷乗越から道は一気に緩やかになりました。ようやく33番の標柱がありましたが、実はこの
標柱、距離が一定の間隔であるわけではないようです。下るにつれて間隔が広がっているよう
です。このため励みにはなりましたが、距離に関してはあまり役に立ちませんでした。
その先も下り道が続きます。この道は倒木が目立ちますが、整備はされていて片付けられています。
今日はここまでにかなりの方とすれ違ったり追い越し、追い越されました。さすがに人気の山です。
また、外国の方が多いのも特徴です。トレランの方もたくさんお会いしました。


緩やかな道 33番の標柱
まだ岩原山、譲葉山、岩倉山と3つの峰が残っています。
さらに進んで、岩原山の分岐点に到着しました。13:45。山頂はここから300mほど先のよう
ですのでパスしました。

岩原山への分岐の標柱
ここからは傾斜が緩くなり、なだらかになった道を下ります。14:10に岩倉山の分岐に到着。
山頂まではほんの30mなので立ち寄りました。分岐からほんの1分で到着した岩倉山山頂は、
木立の中の広場でした。「地味」の一言がぴったりの場所でした。山頂の三角点の横に何故か
地蔵尊が祀られていました。
ちなみに、この山が宝塚市の最高峰(573m)です。
全山縦走の時にはおそらく誰も立ち寄らないのでしょう。分岐からの道は結構荒れ気味でした。



なだらかな道 分岐点 岩倉山山頂
一休みして先に進みます。この先もなだらかな道が続きました。

縦走路
この付近はなんだか道標の間隔が、最初に比べて長くなってきた気がします。
登山道の終点である塩尾寺を目指します。ここからあと20分くらいでしょうか?ですが標高差
は200m近くあります。急な下りが待ち構えている気がします。
道標の番号はどんどん増え、ゆずり葉台方面分岐の看板の所で34番になっています。塩尾寺
の番号は36番なのであと少しです。
ですが、実はこの標識は均等な距離にあるわけではありませんでした。そのため励みにはなり
ましたが、距離や時間の参考にはなりませんでした。
東六甲縦走路では、この標識の積み重なる数字が励みになりました。
予想通り、この辺りの道は急な下りになります。持ってきた杖が大活躍です。それでも疲れも出て
きて足が進みません。
この辺りは雨のせいでしょうか?道の土が流されていて、道自体がガタガタになっている所もありました。
砂山権現神社を過ぎ、最後の階段を下りると山道の先に門が見えてきました。塩尾寺(えんぺいじ)に
14:30に到着です。山の中に忽然と立派なお寺が現れました。境内のベンチで一休みです。


塩尾寺 標柱
登山道はこれで終わりです。ですが、お寺の門前にある標識の通り、ゴールはまだ約3,2km先の
宝塚ゆめ広場です。最後のひと踏ん張りです。
塩尾寺から宝塚までは、長い舗装路を下っていきます。この坂道が意外と曲者で、車道ですが
かなりの急坂です。下りだから楽だと思うとそうではありません。何せお寺の標高が360m。宝塚の
町の標高が50mほどなので300m以上を下るのです。おまけに2日間歩いた疲れが一気に出て、
疲労した足には大きな負担です。足を一歩出す度に膝がガクンと折れてしまいそうになります。
足が悲鳴を上げています。
全山縦走でここまで走り抜いてきた人たちは、どのような気持ちでこの辺りを走るのでしょうか?
10分ほど下ったところに、宝塚市街地が見渡せるところがありました。宝来橋と思われる橋が見え
ます。あそこまでたどり着けは終わりです。

宝塚市街
ところがここからも急な階段が現れました。最後の試練です。手すりにつかまりながら必死で降ります。
その先で車道に合流して2回ほどカーブを曲がると、ここまでとは一転して周辺の光景は住宅地へと
変貌しました。というか完全に町中です。
ほんの30分前とは別世界です。住宅街の中の小路を何度か右左折して、最後に川沿いの道をどん
どん進んでいきます。
ちなみに、マンホールの蓋の絵柄がスミレの花でした。宝塚と言えば宝塚歌劇団。そのテーマソングが
「すみれの花咲く頃」です。思わず口ずさんでしまいました。

すみれの花の絵柄のマンホール
この辺りはまだまだかなり標高が高いです。こんな山の上まで住宅地があるのですね。神戸は坂の町
としても有名ですが、宝塚も同じみたいですね。
この最後の4キロの区間が結構堪えました。ですが最後の意地と根性をみせ、ようやく宝塚の
街中にある宝来橋に到着しました。15:15。駅はまだ少し先ですが、川の手前に「ナチュールスパ
宝塚」という温泉がありますので入浴します。ここでも金宝泉、銀宝泉を楽しめます。
有馬温泉の湯とよく似ていましたので、引き湯しているのかもしれません。疲労回復や筋肉痛
改善の効能があるとされ、六甲全山縦走後の立ち寄り湯にはぴったりです。実に良いお湯でした。
ナチュールスパ宝塚から武庫川を渡ると、ついにゴールの宝塚ゆめ広場に到着です。16:05。
さすがに宝塚、駅前の銅像も歌劇のシーンを再現していました。

阪急宝塚駅前「ゆめ広場」
六甲山全山縦走の旅を無事終えることができました。2年がかりで、2日×2回の4日間で須磨
海岸から宝塚まで合計で約20時間の旅でした。「KOBE六甲全山縦走大会」の時のトレイルラン
の場合は7~8時間程度だそうです。すごいですね。
全山縦走では渋滞が発生するため、余計に時間がかかるのだそうですが、歩く速度は個人に
よって差がありますし、早ければよいという訳でもありません。このHPにもタイムを載せていますが、
参考になればと思い記載しています。決して自慢や競うためではありません。
この長丁場のコースを完走できたことに満足して、宝塚駅から電車で帰路につきました。
昨年に続き、今回も六甲山全山大縦走をやってみました。低山だと甘く見ていたわけではありません
が、めちゃくちゃ疲れました。
コースは登山道も(もちろん道路も)良く整備されており、問題なく歩けました。
標高は低いものの、アップダウンの多さとそれによる累計標高差はアルプスの山に負けないと思います。
山中のルートは道幅の狭いところも多く、シーズン中はかなり混みますので、すれ違ったり追い越したる
する人が多いと思い通りには進めません。十分時間に余裕が必要です。
又、道路を歩く区間も多く、車に注意が必要です。
ですが一度やってみる価値はあると思います。また、全部で10くらいの登山ルートがあるそうですので
機会があれば他のルートにも挑戦してみたいと思います。
皆様も是非どうぞ。