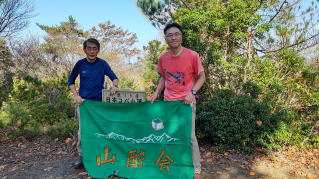いつものように桑名に集合して、登山口の近くにある道の駅奥永源寺渓流の里に向かいます。
東名阪道の桑名ICからR421号で石榑トンネルを越えて道の駅まで1時間ほどです。
このR421号は、以前は山越えの道で、おまけに幅が狭く2トン車以上は通れませんでした。また、
冬は通行止めとなりました。(この旧国道421号線は「酷道」とと呼ばれ、一部のマニアの方の間では
有名な道路だったそうです。)
2011年3月に石榑トンネルが開通し、滋賀県へ通年で簡単に行けるようになりました。峠越えの時は
この区間だけで20分以上かかっていましたが、トンネルだとほんの3分です。
トンネルを抜けて5分ほどで道の駅奥永源寺渓流の里に到着。9:00。道路の反対側に登山者用の
駐車場が造られています。
この先にある永源寺は紅葉の名所として有名です。晴天の土曜日、11月の紅葉の見頃とあって朝から
車が多かったです。登山者用駐車場はすでに満車状態。かろうじて路肩に停めることができました。

登山者専用駐車場
(実は、道の駅の隣にも登山者用の臨時駐車場がありました。こちらに停めればよかったです。この
臨時駐車場は今週と来週の2週の週末だけ使えるようです。)
臨時駐車場を作る程登山者が多いという事なのでしょう。
道の駅でトイレをお借りしました。その駐車場に鈴鹿十座の看板がありました。今後の参考のために
撮影しました。

鈴鹿十座の案内看板
トイレを済ませて9:10にスタート。登山口まで国道を歩き、横道に入り愛知川にかかった橋を渡り
ます。少しわかりにくかったのですが、地元の方に親切に教えていただきました。
流石に11月半ばの山の中を吹く風は冷たく、付近の山には霧雲がかかっていましたが、愛知川に
架かる橋の上から見た紅葉と青く透き通った川のコントラストがとても綺麗でした。


愛知川の流れと紅葉 道横の紅葉
その先で左に曲がって200m程で登山口に到着。登山口は防火用の水槽横にあります。道標と石段
があります。登山口からは階段から始まります。

登山口
石段を登った所に案内看板と登山届BOXがあります。道はすぐに植林された林の中の道になります。

案内看板と登山届BOX
すぐ先に写真の看板がありました。上りの藤川谷ルートには1/18から18/18、下りの政所ルートは
14/14から1/14の標識は200mごとにありました。
ですので、山頂まで3,600mということでしょうか。この看板は役に立ちました。(でも後にも書きます
が、この距離は?でした。)

200m起きの標識
少し先で登山道が崩れていて、鉄橋は崩落しているので左に高巻いて登っていきます。迂回路と
その案内の看板がありましたが、こうした修理はほとんどが山岳会や地元のボランティアによるもの
です。大きな被害が出た時は、もう少し行政が行わないと、いずれ修理する人がいなくなります。
費用は登山者が負担するなどして、きちんと制度化しないといけないと思います。

崩壊箇所
10分ほどで藤川春日神社があり、登山道の右手に石灯籠と鳥居と小さな祠がありました。9:30。
肝心の御社は跡形もなくなっていました。

藤川春日神社
神社を過ぎると、瀬音がしてきてほどなく1回目の渡渉地点に到着。沢に掛けられた木橋で渡ります。
渡渉して藤川谷の左岸沿いの道を進みます。木橋には「気を付けて行ってらっしゃい。」という暖かい
言葉が書かれていました。

渡渉点の木橋
このルートは渡渉が多く、合計すると10回くらいあったと思います。渇水期なのでどの渡渉箇所も水量
は少なかったのですが、飛び石伝いに渡るのはなかなかにスリルがあります。落ちてしまうとこの時期の
水は冷たいです。
渡渉後は、左下に藤川谷を見ながら山腹の道をトラバースして進んでいきます。枯れた支沢の所を2つ
越えます。2つ目は木や岩が散乱していて歩き難かったです。
その先でまた林の中に入ります。結構急な斜面の山腹につけられた道は、幅も狭く、谷側に落ちたら
大変です。
途中で左手が崩落している箇所があり、注意して進みます。やがて、登山道一面に小岩が散乱して
いる所に差し掛かりました。歩き難いです。
ここで4/18の看板を見つけました。2と3は見落としていました。ですが20分足らずで4まで来ました。
少し早すぎる気がします。きっとこの後急斜面などがあり、時間がかかるのでしょう。
登山道は杉林を抜けて紅葉樹林帯へ、また杉林へと目まぐるしく入れ替わります。この辺りの杉林は
きちんと管理されているようです。
それほど傾斜はきつくなく、快調なペースで歩いています。ですが今日も暑くて、登り始めて30分の所
で上着を脱ぎTシャツ姿です。それでも暑くて汗が流れます。
程なく2回目の渡渉地点に到着です。ここもしっかりとした木橋が掛けられていました。10:00。

2か所目の渡渉点の木橋と流れ
2回目の渡渉で右岸に渡ります。この付近は右側が植林、左側が自然林とはっきり分かれています。
その間に付けられた道を登っていきます。涸沢を3回渡り、高巻きを越えて道は次第に傾斜がきつく
なります。

左が広葉樹林 右が植林された杉林
やがて登山道は左に大きくカーブしてきます。その先で3回目の渡渉地点に到着しました。渡渉地点
にはテープなどが巻き付けてあるので分かります。
藤川谷の登山道はよく整備されていて、200mごとにある看板が非常にありがたかったです。
沢の渡渉は渇水期なので岩伝いの渡渉も問題ありません。徐々に高度を上げていきます。
この藤川谷ルートは、渡渉地点以外は沢を離れた高巻きの道で、沢の流れをほとんど見ることが
ありませんでした。登山道はしっかりと整備されているのですが、この時期は落ち葉が地面を覆い
明瞭な踏み跡がわかりません。でもテープや標識などが随所に付けられ、迷う心配はありません。
高度を上げるにつれて日差しが木漏れ日となり、紅葉が鮮やかに見えて晩秋の山歩きの楽しみを
満喫しながら登ります。
再び沢に近づいて、石を頼りに渡渉して右岸に移ると、地面に石灰岩の岩が多くなり歩きにくくなり
ます。薄暗い林の中を通り、登山道は急坂の道になります。また沢に近づき渡渉して、さらに幅の
狭い枝沢を三つほど渡ります。
さらに10分ほど登った所に「豹の穴」という案内があります。10:10着。登山道から7分となっています。
事前に調べたところによると小さな洞窟のようです。パスしました。

豹の穴への分岐点
さらに10分ほど登り、谷が二股に分かれる所で何回目かわからなくなった渡渉をして少し登った後、
左手に回り込みながら、再び藤川谷に沿うように自然林の中の急登を登ります。
10:20に9/18の標識の所に着ました。倒木が登山道を塞ぐように倒れていますが、これが腰掛ける
のにはちょうど良い高さ。まるで座ってくれと言わんばかりの状態です。もちろん腰掛けて休憩。
このコースは、最初は緩やかな登りですが、上部に登るにつれてどんどん傾斜がきつくなるという
困った登山道です。流石にペースが落ち、休憩の回数が増えます。
11/18の標識のところまで20分程かかりました。この後もきつい登りが見えています。
左下に小滝を見ながらトラバース気味に急坂を登っていくと、右手上部に岩壁が見えてきました。
そこにロープが張られた岩場があります。10:45到着。
ロープが掛けられていますが、足場もしっかりしていて問題なく登れます。
岩場の途中に「危険」と書かれた立札があるのがご愛敬です。




岩場
その上部にももう1か所のロープ場がありましたが、手掛かりは十分にあるのでロープは使用せずに
岩の角や木の枝を掴んで慎重に登ると無事に乗り越えられました。
岩場を登り切ったところで左に回り込むとその先に「岩屋⇒」と書かれた標識があります。「奇人の窟」
という洞窟だそうです。
岩屋の入口は小さく、人が一人通れる程度のものです。ところが中に入ってみると結構広い空間が
ありました。ここで修行した方がいるかもしれません。緊急時の避難所としても使えそうです。
でも湿気った嫌な臭いがしましたので早々に退出しました。


洞窟内部
この岩屋の前が今日のコースの中では最も眺望のよい場所でした。ここから東方向に藤原岳、銚子岳
静ヶ岳、竜ヶ岳、釈迦ヶ岳が眺められました。ここで10分ほど休憩。

左から藤原岳、銚子岳、静ヶ岳、竜ヶ岳、釈迦ヶ岳
岩屋の前から登山道に戻り、先に進みます。11:00出発。
岩屋の上からは雑木林の中を登ります。傾斜は緩く快調に進みます。12/18の標識があります。
傾斜の厳しいところは時間がかかり、なかなか数字が進みません。距離だけでなく時間もかいてもらえる
とよいのですが、時間は人によってまちまち。やはり万人に共通となる距離の表示が良いのでしょう。
ここで初めて下山してきた方と会いました。この山は周回コースで登る人が多いそうです。(私達も
ですが)そのためすれ違う人が少ないようです。(ここまで追い抜いた方も一人でした。)
11:10に政所コースとの合流点に到着。帰りはこちらのコースを下ります。13/18の看板があります。

合流点
合流点の先は下りです。それもどんどん下ります。いつものセリフですが、「せっかくここまで登ったの
にもったいない。」が出てしまいます。山頂は最高地点なので、この下った分はこの先で登り返さないと
いけないですし、帰路にこの下った分を当然登らないといけません。2重の意味で困ったものです。
下り道とはいえ5分ほどで14/18の標識の所に着ました。やはりこの標識の位置はおかしいです。
さらに5分ほど下った所で右手から小さな流れがあります。少し先で沢を渡りますが、藤川谷の源流部なの
でしょうか?綺麗な水が流れています。それもかなりの量です。こんな山頂に近いところでこれだけの
水量があるのは不思議です。どこから湧いているのでしょうか?
その先でもう何回目かわからない渡渉をします。(これが最後の渡渉地点でした。)

渡渉箇所
その水のせいで登山道が湿地帯になっている箇所があります。まるで「ヌタ場(猪がドロ浴びをする
ぬかるんだ所)」のようです。そこに落ち葉が積もり、一見すると普通の道に見えて、足を踏み入れると
足首までズッポリ。という箇所があります。私も危うくはまる所でした。登山道から外れたところはかなり
ひどい泥濘の箇所があるようで、立ち入り禁止の看板が立てられていました。
渡渉したところから道は登りになります。どんどん登っていきます。
左手に沢を見ながら進みます。しばらく進むと流れは左手に落ちていき、登山道は右手の斜面を
登っていきます。
17/18の標識がありました。あと200mです。
尾根沿いに登っていきます。鞍部に出てきたら、右手の広い尾根に向かって登っていきます。
それほど急とは思えない登り道ですが、足が重いです。先週四国遍路に出かけて長い距離を歩いた
せいで疲れが残っているのでしょうか?